(2000.10.18) 峠(上下) (司馬 遼太郎 作) 朝日山古戦場に興味を持ったのは司馬遼太郎の「峠」を読んだことによります。 徳川264年の幕藩体制が崩壊し、明治へと大きく時代が変わるとき維新の英雄達とい えば薩摩の西郷隆盛、長州の高杉晋作、土佐の坂本竜馬等が挙げられます。京都から西の 地が一般に幕末明治維新の興味の主要テーマとなっています。 ところが越後長岡に河井継之助という英傑がおり、幕末維新を研究している人達にとっ ては、北越戊辰戦争がもっとも維新の内乱中壮絶な戦争であり、やむなく開戦を決意し、 指揮した河井継之助という人物に興味を持ち研究がなされています。 「峠」を読み、壮絶な北越戊辰戦争に興味を持ち朝日山古戦場をまず尋ねてみました。 以下は新潮文庫の司馬遼太郎作「峠」より抜粋しました。ぜひ一読をお勧めします。
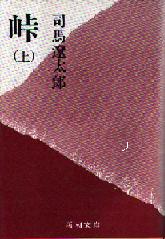
幕末、雪深い越後長岡藩から一人の藩士が江戸に出府しました。 藩の持て余し者でもあったこの男、河井継之助は、いくつかの 塾に学びながら、詩文、洋学など単なる知識を得るための勉学 は一切せず、歴史や世界の動きなど、ものごとの原理を知ろう と努めるのであった。西欧の近代思想にも通じ、柔軟な考え方 を持つ自由人ともいうべき彼は、やがて一藩士から実力によっ て家老に抜擢される。

解明論者であり、封建制度の崩壊を見通しながら、継之助が長 岡藩をひきいて官軍と戦ったという矛盾した行動は、長岡藩士 として生きなければならないという強烈な自己規律によって武 士道に生きたからであった。西郷・大久保や勝海舟らのような 大衆の英雄の蔭にあって、一般にはあまり知られていない幕末 の英傑、維新史上最も壮烈な北越戦争に散った最後の武士の生 涯を描く力作長編。 あ と が き ―――「峠」を終えて――― 人の死もさまざまあるが、河井継之助というひとは、その死にあたって自分の下僕に棺 をつくらせ、庭に火を焚かせ、病床から顔をよじって終夜それをみつめつづけていたとい う。自分というものの生と死をこれほど客体として処理し得た人物も希であろう。身につ いたよほどの哲学がなければこうはではない。 日本では戦国期のひとには、この種の人物はいない。戦国には日本人はまだ、形而上的 なものに精神を託するということがなかった。人間がなまで、人間を興奮させ、それを目 標へ駆り立てるエネルギーは形而下的なものであり、たとえば物欲、名誉欲であった。 江戸時代も降るにしたがって日本人は少しずつ変って行く。武士階級は読書階級になり、 形而上的思考法が発達し、ついに幕末になると、形而上的興奮をともなわなければかれら は動かなくなる。言葉をかえていえば、江戸三百年という教養時代が、幕末にいたってそ れなりに完成し、そのなかから出てくる人物たちは、それぞれ形はかわってもいずれも形 而上的思考法が肉体化しているという点では共通している。志士といわれる多くの人々も そうであり、賢候といわれる有志大名たちもそうであった。かれらには戦国人のような私 的な野望というものが、まったくといっていいほどすくない。 人はどう行動すれば美しいか、ということを考えるのが江戸の武士道倫理であろう。人 はどう思考し行動すれば公益のためになるかということを考えるのが江戸期の儒教である。 この二つが、幕末人をつくりだしている。 幕末期に完成した武士という人間像は、日本人がうみだした、多少奇形であるにしても その結晶のみごとさにおいて人間の芸術品とまでいえるとように思える。しかもこの種の 人間は、個人的物欲を肯定する戦国期や、あるいは西洋にはうまれなかった。サムライと いう日本語が幕末期からいまなを世界語でありつづけているというのは、かれらが両刀を 帯びてチャンバラをするからでなく類型のない美的人間ということで世界がめずらしがっ たのであろう。また明治後のカッコワルイ日本人が、ときに自分のカッコワルサに自己嫌 悪をもつとき、かつての同じ日本人がサムライというものをうみだしたことを思いなおし て、かろうじて自信を回復しょうとするのもそれであろう。私はこの「峠」において、侍 とはなにかということを考えてみたかった。それを考えることが目的で書いた。 その典型を越後長岡藩の非門閥家老河井継之助にもとめたことは、書き終えてからもま ちがっていなかったとひそかに自負している。 かれは行動的儒教といういうべき陽明学の徒であった。陽明学というのは、その行者た るものは自分の生命を1個の道具としてあつかわなければならない。いかに世を済うかと いうことだけが、この学徒の唯一の人生の目標である。このために、世を済う道をさがさ ねばならない。学問の目的はすべてそこへ集中される。 云々 kentousi (大塩平八郎の乱) 陽明学徒には江戸時代大阪で士農工商の身分制の中で自ら役人の身でありながら 役人の腐敗に憤りを感じ百姓町人の為決起した大塩平八郎という人物がいます。 ご意見ご感想をお待ちしています。